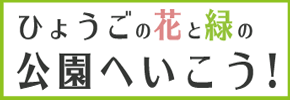デンドロビウム・エキスポ2025・大阪関西・ジャパン
【展示室2】
大阪・関西万博のために特別に品種改良された記念のラン、
「Dendrobium EXPO2025 Osaka Kansai Japan」が開花しました!
このランは、日本とシンガポールの外交関係樹立59周年を迎えた、2025年4月26日に開催されたシンガポールパビリオンのグランドオープニングセレモニーにてお披露目され、その後、あわじグリーン館に贈られました。
その後、当館にて栽培管理し、2025年8月18日、初めて開花しました。
団結と革新を象徴する赤と青が調和した鮮やかな紫色で、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が表現されています。
現在、開花中です!ミャクミャクカラーを眺めながら、大阪・関西万博を振り返ってみませんか?
学名:Dendrobium EXPO2025 Osaka Kansai Japan
(Dendrobium Isobel Barstow × Dendrobium Ow Foong Pheng)
植物分類:ラン科デンドロビウム属
※2025年にシンガポール植物園によって英国王立園芸協会に登録。


ハイドゥンツバキ(カイドウツバキ)
【特別展示室】
約100年以上前に発見されていますが、現在までほとんど知られていなかった種です。
高さ2~3mになる半耐寒性常緑低木で、樹々の下などの暗い場所に生育するツバキの仲間です。ほとんどのツバキは頂生(ちょうせい)といって、枝の先に花を付けますが、この種は腋生(えきせい)、つまり葉のつけねの部分に花を付けるタイプです。
花の色は桃紅色、質感もこれまでにはない肉厚で、蝋細工のように美しい花が魅力です。花弁は6弁以上つき半八重に見えます。また、白花品種も存在しており、清らかさを象徴するような純白の花を咲かせます。赤みを帯びた新芽との対比が美しいのも特徴です。当館では、白花も栽培展示を行っており、時期によっては、紅白同時開花を迎えます。※2026年2月19日(木)現在、白花も開花中です!※


231228-4-1024x768.jpg)
カイドウツバキ(海棠椿)とも呼ばれ、ベトナム語で「海棠」は「Hi Duong」、日本語では「ハイドゥン」「ハイドン」と呼ばれています。ベトナムのテト(旧正月)にはこの花が使われるようです。
2018年時点で、国際自然保護連合(IUCN)により野生では絶滅したと宣言されており、現在は植物園や栽培下でのみ生き残っています。
学名:Camelia amplexicaulis
和名:カイドウツバキ
別名:ハイドゥン(Hi Duong)、ベトナム椿
植物分類:ツバキ科ツバキ属
原産地:ベトナム北部
ヒメシャリンバイ(姫車輪梅)
【展示室3】
春、枝先に梅に似た清楚な白い花を咲かせる常緑の低木です。
枝が車輪のように放射状に広がる姿と、花の形が梅に似ていることからその名がつきました。
一般的なシャリンバイよりも葉が小さく、厚く光沢のある葉は、乾燥や潮風に耐える強い性質を持っています。樹高は最大1.5mほどで成長も緩やかなため、庭木や生け垣として人気です。


春の新芽は赤く色づき、冬には寒さで葉が美しい赤銅色に紅葉します。
白い花が開花した後には小さな実がなり、秋には黒紫色に熟すなど、季節ごとに色彩の変化を楽しめる植物です。
学名:Rhaphiolepis indica var. umbellata f.minor
分類:バラ科シャリンバイ属
原産地:日本(本州~沖縄)、東アジア
アングレカム・レオニス
【展示室2】
アングレカム・レオニスは、小型の着生ランで、革質の葉は鎌状をしており、最大で25.4 cmまで成長します。葉は茎に沿って一列に並び、各葉は前の葉と180度の角度で交互に配置されます。
花は1〜7個の花序に咲き、白い星形の花をつけます。花は長持ちし、ジャスミンに似た甘い香りが特徴です。萼片と花弁は広がり、花の直径は最大約10 cmに達します。
花色は白から淡い緑色で、基部は広く、先端に向かって細くなっています。
ラン科特有の唇弁は他の花弁より大きく、ずい柱と融合して花粉と胚珠を囲みます。
唇弁は基部に長い距があり、特徴的な形状をしています。
学名:Angraecum leonis
植物分類:ラン科アングレカム属
原産地:コモロ諸島、マダガスカル
パピリオナンセ・テレス
【展示室5】
パピリオナンセ・テレスは、ネパール東部、ブータン、インド北東部から、ミャンマー、タイ、ラオス、ベトナム、中国南部にかけて広く分布し、アンダマン諸島およびニコバル諸島でも確認されている着生ランです。このタイプのランの中でも、特に知名度が高く、分布域の広い代表的な種として知られています。


標高 250~850m の地域に自生し、タイでは各地で見られますが、特にドイ・ステープ(タイ北部チェンマイ近郊のステープ山頂)やメーホンソーン(タイ北西部、ミャンマーとの国境に位置する県)、
チェンライ(ミャンマー、ラオスと国境を接するタイ最北端の県)など、北西部の山岳地帯に大きな自生群落があります。
本種は 1915年、フリードリヒ・リヒャルト・ルドルフ・シュレヒターによって記載されました。

細長い円筒状の葉を持ち、蝶が舞うような優雅な花を咲かせるのが特徴です。
花色はピンクからマゼンタ系が多く、個体によっては濃い模様が入ります。
単茎性の着生ランで、一本の茎に沿って葉をつけ、上向きに成長します。
暖かく湿度のある環境と十分な日光を好み、木などに着生させて育てることができます。
学名:Papilionanthe teres
別名:棒バンダ
植物分類:ラン科パピリオナンセ属
原産地:東ヒマラヤ、中国南中部、南・東南アジア
オンシジウム・シャリーベイビー ‘スウィートフレグランス’
【展示室2】
オンシジウム・シャリーベイビー ‘スウィートフレグランス’ は、10 月から 3 月にかけて、深い赤と白の小さな花をたくさん咲かせる人気のランです。
背が高くしなやかに伸びる花茎の先にびっしりと花をつけ、ふんわりと漂う甘い香りが魅力の品種です。特に朝から午後の早い時間にかけて、濃厚なチョコレートの香りが最も強く感じられます。
栽培しやすいことでも知られており、花茎は 約 60 cm以上に伸びることも。
開花期になると、甘い香りが数週間もお部屋いっぱいに広がります。
チョコレート好きの方にも、香りのよいランをお探しの方にも、ぜひ育ててみてほしいおすすめの品種です。
学名:Oncidium Sharry Baby ‘Sweet Fragrance’
植物分類:ラン科オンシジウム属
ウツボカズラ(ネペンテス)
【テラス】
熱帯アジアにすんでいる「ウツボカズラ(ネペンテス)」。
ウツボカズラは、つるのようにのびて他の植物にからまりながら育ちます。
葉っぱの先がふくらんでできる“ふくろ”が、虫とりのわなになっています。
フタの裏にはあまい蜜が出るところがあり、いいにおいで虫をおびきよせます。
入り口はツルツルしていて、虫はすべって中に落ちてしまいます。
中には強い消化液がたまっていて、虫は出られません…!
小さなものは小指サイズでかわいいですが、大きいものはなんと45cmもあって、
ネズミまでとらえてしまうことも!
2022年8月20日(土)に、兵庫県立フラワーセンターが栽培する食虫植物ウツボカズラの一種
「ネペンテス・トランカータ」の捕虫袋が、 公式記録55.5㎝で世界最長の捕虫袋として、
世界記録に認定されました。
ちなみに、この”ふくろ”の上にフタは、虫を閉じこめるためではなく、雨よけなのです!
学名:Nepenthes
植物分類:ウツボカズラ科ウツボカズラ属
原産地:東南アジア
セファロタス・フォリキュラリス
【テラス】
セファロタスは、オーストラリア南西部の湿地にだけ自生する、とても珍しい食虫植物です。
「1属1種」しか存在しない特別な仲間で、植物の世界でも貴重な存在です。
葉が変化してできたつぼ型の“ピッチャー”で虫をとらえる点は、ウツボカズラやサラセニアとよく似ていますが、分類的にはまったく別の植物です。
セファロタスのピッチャーは、小さいながらもよくできていて、
・虫を誘導するための中央のひだ(フランジ)
・2本の側翼には細かい毛が密生
これらの構造で、地面を歩く虫(とくにアリ)を、うまくピッチャーの口まで導きます。
蜜のにおいに誘われた虫は、中へ入った瞬間につるつる滑って底に落下!
中には消化酵素の入った液体があり、虫はやがて消化されて栄養になります。
いったん落ちると、内側の段差や形状により脱出できません。


学名:Cephalotus follicularis
植物分類:セファロタス科セファロタス属
(フクロユキノシタ科フクロユキノシタ属)
原産地:オーストラリア南西部
クレロデンドルム・スペキオスム(ベニゲンペイカズラ)
【展示室2】
クレロデンドルム・スペキオスム(Clerodendrum × speciosum)は、アフリカ原産のゲンペイクサギ(Clerodendrum thomsoniae)とベニバナクサギ(Clerodendrum splendens)の交配種です。
名前のとおり華やかで見事な常緑つる性低木です。
ハート形の葉に、夏から秋にかけて赤い花と、つぼみの頃は桃色、開花時には白っぽく変化する美しい苞を房状につけ、そのコントラストがとても魅力的です。秋には青い実をつけることもあります。
(熱帯西アフリカ)シソ科クサギ属1-1024x768.jpg)
(熱帯西アフリカ)シソ科クサギ属2-1024x768.jpg)
濃緑色で深い葉脈の葉と、長い茎の先端に咲く花姿は存在感があり、日向から日陰まで幅広い環境に順応するため、育てやすいのも魅力です。トレリスやフェンス、アーチ、柱などに誘引することでより美しく仕立てることができ、風を避けられる場所での地植えが特に向いています。
鮮やかな花色が季節を通して楽しめる、観賞価値の高いつる植物です。
学名:Clerodendrum × speciosum
植物分類:シソ科クサギ属










 現在開花中のお花
現在開花中のお花 
260216-1-300x225.jpg)






(熱帯西アフリカ)シソ科クサギ属1-300x225.jpg)


231228-4-1024x768.jpg)














(熱帯西アフリカ)シソ科クサギ属1-1024x768.jpg)
(熱帯西アフリカ)シソ科クサギ属2-1024x768.jpg)
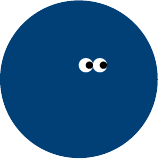




 インフォメーション
インフォメーション